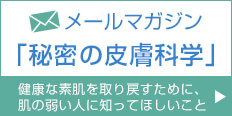資料室
2006年11月08日
界面活性剤の秘密
界面活性剤の種類によって、タンパク変性作用の強さ、刺激の強さに差があるといわれています。しかし、あくまで他の種類との比較の話であって、タンパク変性作用が弱いといわれている非イオン系界面活性剤は、「膜タンパク可溶化剤」(タンパク変性剤)として使用されています。皮膚への影響を考えると、なるべく接触を避けることが望ましいと言えます。
界面活性剤について一般的にいわれていることを冷静に考えると・・・
界面活性剤はお肌につけてはいけない物質ですね。
―界面活性剤について一般的にいわれていること―
界面活性剤とは
界面活性剤は表面張力を弱める作用を持つ物質である。界面(表面)とは、2つの性質の異なる物質の境界面のことであり、2つの混じり合わない物質の間には、必ず界面が存在する。界面活性剤とは、このような界面に働いて、界面の性質を変える物質のことをいう。通常、親水基(水になじみやすい部分)と疎水基(もしくは親油基・水になじみにくい部分)を併せ持つ。
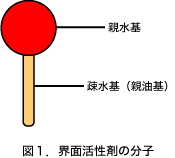
ミセル形成と可溶化<
界面活性剤を少しずつ水に溶かしていく場合、界面活性剤の親水基は水の中に入ろうとし、一方で疎水基は水との接触を避けようとするので、界面活性剤の分子は主に空気と接する水の表面に吸着し、配列していく。しかし、界面活性剤の濃度を徐々に濃くしていくと、疎水基は逃げ場がなくなり、徐々に寄り集まって水との接触を避けるようになる。
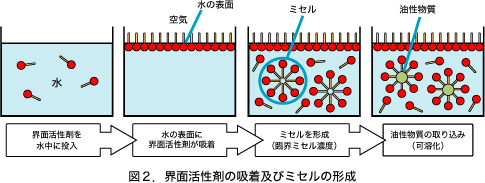
そして、ついには、親水基を外側に向け、疎水基を内側に向けた形の集合体を形成し始める。この集合体をミセルといい、疎水基が水との接触を回避しようとするには、界面活性剤の分子が数十個から100数十個集まった集合体になる必要がある。また、ミセルが出来始める時の界面活性剤の濃度を臨界ミセル濃度(critical micelle concentration略してcmc)という。
ミセルは、中心部が疎水性、つまり油となじみやすい性質のため、水に溶けにくい油性の物質を、ミセルの内部に取り込むことが出来る。この現象を可溶化と呼ぶ。可溶化は、洗浄に寄与する界面活性剤の働きの一つである。
乳化と分散
通常、水と油を混ぜて振ると、一時的に混ざるがすぐに分離してしまう。ところが、そこに界面活性剤を入れて振ると、白く濁ったようになって分離することなく混ざる。この現象を乳化という。水と油の間の界面には、表面張力が働いており、混ざっている時には、水の中にたくさんの油滴が出来ているので、界面の面積が広くなっている。表面張力が強いと、界面の面積は出来るだけ小さくなろうとするので、水は水同士、油は油同士でまとまって、界面の面積を最小にする。
ところが、界面活性剤が溶けていると、表面張力が小さくなるので、たくさんの油滴ができて界面の面積が広いままでも、安定していられるようになる。乳化している時、油滴と水の間の界面には、疎水基を内側(油側)に、親水基を外側(水側)に向けて、界面活性剤の分子が吸着している。可溶化と似ているが、油滴はミセルよりもはるかに大きく、目に見える規模の粒なので、油が可溶化している液は透明に見え、油が乳化している液は白く濁って見えるという違いがある。
例えば、マヨネーズにおいては、卵黄の脂質(リン脂質やステロール類等)が界面活性効果を表し、牛乳においてはカゼイン等の乳タンパク質が働くことで安定した乳化を形成している。 また、乳化と似た現象で、分散という現象がある。すすなどの固体の粒子を水に入れて振ると、油の時と同じように、粒子同士が集まって水と分かれようとするが、界面活性剤を入れて振ると、粒子の周りに界面活性剤の分子が吸着して、水の中に散らばって安定する。
皮膚の洗浄における界面活性剤の働き
界面活性剤は汚れの表面に吸着して、汚れと水との間の表面張力を小さくするため、汚れが皮膚からはがれて水の中に浮き上がろうとする。そして、タオルなどの摩擦による力も手伝って、汚れが水中に浮き上がると、乳化、分散、可溶化という働きによって水の中に安定に浮かび、汚れの表面と皮膚の表面はどちらも界面活性剤の分子に覆われるので、汚れが再付着しにくくなる。
洗浄における界面活性剤の働きが充分に発揮されるためには、ミセルが必要となる。それ以上吸着できる界面がなくなって界面活性剤同士で集まり始める濃度、つまり臨界ミセル濃度以上なら、ミセルを作っている分子が汚れが浮き上がって出来た新しい界面に吸着することが可能となる。よって、効果的な洗浄のためには、臨界ミセル濃度以上の濃度が必要であるといえる。
界面活性剤の弊害
界面活性剤には「タンパク変性作用」と呼ばれる性質があり、皮膚のタンパク質を破壊する働きを持っている。慢性的な肌荒れを起こしている人は、ボディシャンプーや台所用の洗剤、または化粧品等によって皮膚のタンパク質を一部破壊されている場合が多い。タンパク変性作用による皮膚への影響としては、アトピー性皮膚炎・手荒れ・湿疹・かぶれ等の一次刺激性接触皮膚炎が挙げられる。
また、界面活性剤には浸透力があるため、シャンプーや歯磨き粉を使うと、頭皮、頭髪、舌の細胞などが傷つけられたり、肝臓障害などの原因になると指摘されているが、それらの主な論拠はこの「タンパク変性作用」と「皮膚からの強力な浸透力」という2つの性質にある。
タンパク変性作用のメカニズム
タンパク変性作用には、界面活性剤の親水基の種類が影響しているといわれている。例えば、ケラチンタンパクの変性実験ではAS(高級アルコール硫酸エステルナトリウム)、LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)などの陰イオン界面活性剤が変性作用が大きく、石けん(脂肪酸塩)がそれに続き、非イオン界面活性剤は変性作用が少ないとされている。
一言で界面活性剤といっても、その用途は非常に広くなっている。洗濯用洗剤・住居用洗剤等の洗浄力を重視するものはLASやASF等の陰イオン界面活性剤が主として使用され、台所用食器洗剤等の洗浄力と皮膚への影響のバランスを重視するものは、AES等の陰イオン界面活性剤やAO等の両性界面活性剤、AE等の非イオン界面活性剤が数種混合されて使用される。
化粧品の中でも、シャンプー・洗顔料等と乳液・クリーム等では、使用する界面活性剤の種類が異なる。シャンプー・洗顔料等は洗浄を目的としているため、洗浄力の高い陰イオン界面活性剤が主として使用される。シャンプーはASやAES等の高級アルコール系陰イオン界面活性剤が基剤として使用され、両性界面活性剤や非イオン界面活性剤が補助的に配合されるものが多いが、洗顔料は石けんやアミノ酸系の陰イオン界面活性剤が使用される。また、トリートメントには、毛髪のタンパク質に吸着しやすい陽イオン界面活性剤が帯電防止剤として用いられる。乳液・クリーム等は塗布時間が長く、皮膚への影響が最も重視されるため、比較的刺激が少ないとされる非イオン界面活性剤が主に乳化目的で使用される。
界面活性剤とイオン
界面活性剤は、水に溶かした時に電離してイオン(電荷をもつ原子又は原子団)となるイオン性界面活性剤と、イオンにならない非イオン(ノニオン)性界面活性剤に大きく分類される。イオン性界面活性剤はさらに、陰イオン(アニオン)界面活性剤、陽イオン(カチオン)界面活性剤及び両性界面活性剤に分類される。また、イオン性による分類に加え、親水基や疎水基の種類や原料によってさらに細かく分類される。
陰イオン(アニオン)界面活性剤
水に溶けた時に、親水基の部分が陰イオンに電離する界面活性剤。洗浄力が高いため、石けんや合成洗剤に多く利用され、その利用量は全界面活性剤の約半分を占めているといわれている。陰イオン界面活性剤は、親水基としてカルボン酸、スルホン酸、あるいはリン酸構造を持つものが多い。カルボン酸系としては石けんの主成分である脂肪酸塩が、スルホン酸系としては合成洗剤に多く使われる直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(LAS)や、アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム(AOS)がある。
| 分 類 | 系 統 | 別 名 |
| 脂肪酸系(陰イオン) | 純石けん分(脂肪酸ナトリウム) | 石ケン素地、脂肪酸Na、ヤシ脂肪酸Na、ラウリン酸Na 等 |
| 純石けん分(脂肪酸カリウム) | 石ケン素地、脂肪酸K、ヤシ脂肪酸K、オレイン酸K 等 | |
| アルファスルホ脂肪酸エステルナトリウム | ASF 等 | |
| 直鎖アルキルベンゼン系 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム | LAS 等 |
| 高級アルコール系 (陰イオン) | アルキル硫酸エステルナトリウム | AS、ラウリル硫酸Na 等 |
| アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム | AES、ラウレス硫酸塩 等 | |
| アルファオレフィン系 | アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム | AOS、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na 等 |
| ノルマルパラフィン系 | アルキルスルホン酸ナトリウム | SAS、アルキル(C14-18)スルホン酸Na 等 |
陽イオン(カチオン)界面活性剤
水に溶けた時、親水基の部分が陽イオンに電離する性質を持つ。親水基としてテトラアルキルアンモニウムを持つものが多い。石けんと逆のイオンになっているため、「逆性石けん」と呼ばれることもある。一般に、マイナスに帯電している固体表面に強く吸着し、柔軟性、帯電防止性に優れ、柔軟仕上げ剤やリンス、トリートメントに使用されている。また、細菌の表面はマイナスに帯電している事が多いため、殺菌剤としても使われている。
| 分 類 | 系 統 | 別 名 |
| 第四級アンモニウム塩系 | アルキルトリメチルアンモニウム塩 | ラウリルトリモニウムクロリド、セトリモニウムクロリド 等 |
| ジアルキルジメチルアンモニウム塩 | ベンザルコニウムクロリド、ステアラルコニウムクロリド 等 |
両性界面活性剤
分子内にアニオン性部位とカチオン性部位の両方を併せ持っているため、水に溶けた時、アルカリ性領域では陰イオン界面活性剤の性質を示し、酸性領域では陽イオン界面活性剤の性質を示す。洗浄力が強く、殺菌作用、毛髪柔軟効果がある。刺激性がほとんど無いため、シャンプーやリンス、柔軟剤等に用いられる。
| 分 類 | 系 統 | 別 名 |
| アミノ酸系 | アルキルアミノ脂肪酸ナトリウム | ココアンホ酢酸Na 等 |
| ベタイン系 | アルキルベタイン | ラウリルベタイン 等 |
| アミンオキシド系 | アルキルアミンオキシド | AO、ココアミンオキシド 等 |
非イオン(ノニオン)界面活性剤
水に溶けた時、イオン化しない親水基を持っている界面活性剤で、水の硬度や電解質の影響を受けにくく、他の全ての界面活性剤と併用できる。酸性でもアルカリ性でも使用でき、化学的に安定している。また、乳化作用、分散作用、浸透作用に優れているため、化粧品や食品の乳化剤としても多く使用される。食品衛生法で食品に使うことのできる界面活性剤は、レシチン(両性界面活性剤)を除き、全て非イオン界面活性剤である。また、洗濯用洗剤もポリオキシエチレンアルキルエーテル(AE)等の非イオン界面活性剤を使用したものが増加傾向にある。
| 分 類 | 系 統 | 別 名 |
| 脂肪酸系(非イオン) | しょ糖脂肪酸エステル | SE、ステアリン酸スクロース 等 |
| ソルビタン脂肪酸エステル | ラウリン酸ソルビタン、ステアリン酸ソルビタン 等 | |
| ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル |
ポリソルベート40等 |
|
| 脂肪酸アルカノールアミド | DA(AZ)、コカミドDEA 等 | |
| 高級アルコール系 (非イオン) | ポリオキシエチレンアルキルエーテル | AE、(C12-14)パレス-7等 |
| アルキルフェノール系 | ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル | APE、オクトキシノール-9等 |
非イオン界面活性剤は、タンパク変性作用が弱いといわれているが、膜タンパク可溶化剤(タンパク変性剤)として使用されている。あくまでイオン性界面活性剤との比較の話である。
石けんも合成界面活性剤である
界面活性剤のうち、脂肪酸ナトリウム、脂肪酸カリウムを「石けん」と呼び、それ以外は一般的に「合成界面活性剤」と呼ばれている。また、純石けん分が97%以上の石けんを「純石けん」と呼ぶ。
石けんは古くから使用されて来た洗浄剤であり、脂肪酸系の陰イオン界面活性剤に分類される。界面活性の理論が確立されるまでは、最も多く使用されていた。浴用石けんは、通常、牛脂70~80%、ヤシ油またはパーム核油20~30%の配合から成っているが、洗濯石けんの場合は、牛脂を主成分とし、大豆油や米ぬか油等が水への溶解性を高める目的で配合されている。また、近年はパーム油を原料にしたものが増えている。
油脂の鹸化または脂肪酸の中和によって作られる。油脂鹸化法は牛脂、ヤシ油、パーム油、オリーブ油などの動植物油脂と水酸化ナトリウム(NaOH)を用いて鹸化し、多量の食塩を加えて塩析させて分離する。脂肪酸中和法は脂肪酸をアルカリで中和させて作るため、残留塩基がなくなり、皮膚や粘膜に対して刺激が少ない石けんが得られる。また、油脂にメチルアルコールを反応させ、エステル交換によって脂肪酸メチルエステルを作り、これをアルカリで鹸化する「エステル鹸化法」という製法もある。
排水後、水中のカルシウムイオンやマグネシウムイオンと結合することにより金属石けん(石けんカス)となり界面活性力を失う事や、生分解性が良好であるため環境にやさしいといわれている。
しかし一方で、水の硬度により使用量が多くなることや、有機物を多く含むことによる有機汚濁負荷、そして製造時の油脂消費量の多さ、高いエネルギーコストなどの側面もあり、省エネ・省資源の観点から環境への影響が無視できないものとなっている。
pHと皮膚の関係
「弱酸性だからお肌にやさしい」と謳っている商品が数多く存在するが、弱酸性と中性の洗浄料とを比較した時に、その液性の違いによる皮膚への影響がどの程度なのかは明らかになっていない。しかし、これらの弱酸性・中性の洗浄料と、アルカリ性の洗浄料を比較した場合、そのアルカリによる皮膚への影響は大きくなる。
人間の皮膚は酸性に強く、アルカリ性に弱いという性質を持っており、健康な皮膚は皮脂・汗・皮膚常在菌等によって酸性に保たれている。強度の酸やアルカリが皮膚に触れると、皮膚熱傷に似た傷害である化学損傷を生じる。酸による傷害は通常は浅いもので、 度~ 度熱傷(表皮熱傷~浅達性・深達性熱傷)に相当し、発赤、水疱、びらんを伴う。薬品の種類によっては緑黒色や暗褐色(硫酸)、黄褐色(硝酸、塩酸)、白色(フェノール)を呈する。一方、アルカリによる傷害は皮膚の深層にまで及んでいることが多く、 度熱傷(皮下熱傷)に相当し、蒼白でなめし皮のようになる。
洗濯用洗剤の多くは弱アルカリ性で、また、皮膚洗浄剤では、石けんなどの一部の製品が弱アルカリ性である。アルカリ性の洗剤の特性として洗浄力の高さが挙げられるが、これはそのまま皮膚に接触した際の皮膚へのダメージの大きさに直結する。アルカリの水溶液は膨潤作用を持ち、タンパク質を水に溶解させる。このため、皮脂膜は容易に脱落し、皮膚に直接アルカリが作用する。アルカリが皮膚につくとヌルヌルするのは、皮膚表面がタンパク変性を起こしているためである。
界面活性剤は本質的に肌を傷めるものである
界面活性剤は、その種類によってタンパク変性作用の強さや刺激性に差があるといわれているが、基本的に肌を傷める原因となる事実は変わらない。特に石けん等のアルカリ性界面活性剤は、界面活性剤のタンパク変性作用に加え、アルカリ変性作用も加わるため、使用を控えるべきである。
界面活性剤の皮膚への影響を考えると、極力接触を避けることが望ましいと言える。
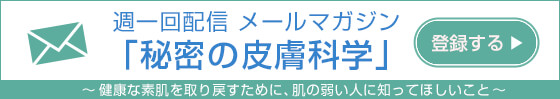
関連性の高い記事
- 改善が停滞?『洗濯洗剤の影響』の秘密 | 第799号
- リアルな声?『測定にいらしたフェローのご質問』の秘密 | 第793号
- 機能がたくさん?『洗濯洗剤』の秘密 | 第785号
- 洗浄力が必須?『洗濯洗剤は使いましょう』の秘密 | 第777号
- 肌の状態アンケート?『いただいたご質問から』の秘密 | 第743号
- 日用品の基礎知識?『医師用テキスト ~洗濯洗剤編~』の秘密 | 第709号
- 対策は簡単?『冬の静電気の防ぎ方』の秘密 | 第696号
- 成分を確認?『入浴剤の選び方』の秘密 | 第692号
- 第666号 肌に影響ある?『界面活性剤不使用の洗濯洗剤』の秘密
- 第522号 基本のおさらい『化粧品』の秘密
- 化粧品によく使用される界面活性剤・シリコーン
- 第374号 "指定"のワケ 『洗濯洗剤の切り替えを!』の秘密(1)
- 第370号 取捨選択?『ちまたに溢れる美容情報』の秘密
- 第337号 基準にできる?『肌に合う・合わない』の秘密
- 主要油脂原料の脂肪酸組成(%)
- 第127号 必ず閉じる?『開いた毛穴』の秘密
- 第121号 お肌にやさしい?『天然系界面活性剤』の秘密(2)
- 第120号 お肌にやさしい?『天然系界面活性剤』の秘密
- 第107号 クリームでお肌を守る?『あやしい情報にご用心』の秘密
- 第88号 フツウに洗顔しているだけなのに!?『原因不明のブツブツ』の秘密
- 第19号 ホントにやさしい?『弱酸性』の秘密
【次のエントリー】
→お湯洗髪成功レポート
【前のエントリー】
→にがりについて
![]()