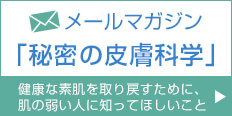バックナンバーメールマガジン「秘密の皮膚科学」
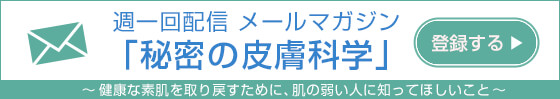
2025年09月30日配信
皮膚科の傾向は?『医療費の動向』の秘密 | 第861号
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2025/09/30━☆
健康な素肌を取り戻すために知ってほしいこと
「秘密の皮膚科学」
第861号 発行者:シニアフェロー 牛田専一郎
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
みなさん、こんにちは。
シニアフェローの牛田専一郎です。
今週は毎年恒例の医療費のお話です。
「医療費って年々上がってる印象ですが......」
そうですね。
どのくらい上がっているのか見ていきましょう。
☆-------------------------------------------------------☆
皮膚科の傾向は?
『医療費の動向』の秘密
☆-------------------------------------------------------☆
▼医療費って?
「医療費といってもあまり
ピンと来ないのですが」
ひとことで「医療費」と言っても、じつは
薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、
訪問看護医療費などいろいろな種類があります。
診療所や病院で治療を受けた時、
保険証があれば、原則として自己負担は3割。
みなさんが毎月納めている保険料で残り7割をまかなっています。
医療費は、この医療保険による給付、さまざまな
公費負担医療制度による給付、自己負担に
よって支払った医療費を合計したものとなります。
「複雑......」
▼医療費の変化は
厚生労働省では毎年8月末に前年度の
医療費の動向が発表されています↓
☆医科・歯科・調剤医療費の動向調査:集計結果
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/cyouzai_doukou_itiran.html
令和6年度の概算医療費は48兆円。
前年度比1.5%増でした。
◇概算医療費(単位:兆円)
令和元年度 43.6
令和2年度 42.2
令和3年度 44.2
令和4年度 46.0
令和5年度 47.3
令和6年度 48.0
「4年連続で過去最高なんですね」
ええ。
高齢化や医療技術の高度化が原因とされています。
診療科別に見るとこんな推移になっています↓
https://hisesshoku-derm.com/archives/2025/09/post_16.php
「これを見ると逆に減っているのは......
内科、小児科、外科、耳鼻咽喉科ですね?」
そうですね、白木さん。
増えているのは整形外科、皮膚科、
産婦人科、眼科です。
▼皮膚科が伸びているのは?
「皮膚科は伸びているんですね」
ええ。そのようですね。
皮膚科の調剤医療費を見てみましょう。
令和6年度は5,775億。
前年度から1,669億伸びています。
「ずいぶんと増えていますね。
いったい何が増えているんでしょうか」
令和6年度も注射薬で大幅な伸びが見られました。
◇「注射薬」薬剤料(単位:億円)
平成30年 4
令和元年 30
令和2年 54
令和3年 105
令和4年 152
令和5年 239
令和6年 671
「すごい伸びですね!
でも皮膚科で使う注射薬ってなんでしたっけ」
白木さん......。
思い出してくださいね。
タンパク質をもとに作られた生物学的製剤です。
アレルギー性の炎症の原因となるIL-4/IL-13シグナル伝達を
阻害する、免疫調整薬です。
皮膚科ではおもにアトピー性皮膚炎の
治療に使われています。
アトピー性皮膚炎治療薬は
さまざまなメーカーの開発が進んでおり、
副作用が起きにくい、投与頻度が少ないなどの
注射薬も開発されてきているようです。
▼アトピー性皮膚炎診療ガイドラインの改訂
相次ぐ新規薬剤の発売を受けて、2024年、
3年ぶりに「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン」が
改訂されました。
注射薬を含む新規薬剤5種が
掲載され、使用が強く推奨されています。
「それで薬剤料が増加しているんですね」
そうですね、白木さん。
こうした新薬の使用対象が、
「重症・最重症・難治性状態」(2018年版)から
「中等症以上の難治状態」(2021年版)に変更されています。
より幅広い患者さんに、
さまざまな新規薬剤を使用できるようになったことが
増加の一因でしょう。
これまでのステロイドの塗布だけでなく、
注射薬や経口薬など「全身療法」が
取られるようになってきたのですね。
今年度の医療費はどんな動向で推移しているのか。
また来年発表されたらお知らせしますね。
▼お知らせ:用語の変更です
『非接触生活』→『非侵襲生活』に。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆侵襲とは:
生体の内部環境の恒常性を
乱す可能性がある刺激全般をいう。
ここでは、皮膚の内部環境(バリア機能:細胞間脂質)
の恒常性を乱す要因です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
侵襲を受けやすい肌体質の人が、侵襲を受けない
生活(『非接触生活』→『非侵襲生活』)をしましょう、
ということです。
研究会としてこの方法をわかりやすく
知ってもらう活動を続けていきます。
☆ご相談・ご質問など、お気軽にどうぞ
皮膚科の傾向は?
『医療費の動向』の秘密
☆-------------------------------------------------------☆
▼医療費って?
「医療費といってもあまり
ピンと来ないのですが」
ひとことで「医療費」と言っても、じつは
薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、
訪問看護医療費などいろいろな種類があります。
診療所や病院で治療を受けた時、
保険証があれば、原則として自己負担は3割。
みなさんが毎月納めている保険料で残り7割をまかなっています。
医療費は、この医療保険による給付、さまざまな
公費負担医療制度による給付、自己負担に
よって支払った医療費を合計したものとなります。
「複雑......」
▼医療費の変化は
厚生労働省では毎年8月末に前年度の
医療費の動向が発表されています↓
☆医科・歯科・調剤医療費の動向調査:集計結果
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/cyouzai_doukou_itiran.html
令和6年度の概算医療費は48兆円。
前年度比1.5%増でした。
◇概算医療費(単位:兆円)
令和元年度 43.6
令和2年度 42.2
令和3年度 44.2
令和4年度 46.0
令和5年度 47.3
令和6年度 48.0
「4年連続で過去最高なんですね」
ええ。
高齢化や医療技術の高度化が原因とされています。
診療科別に見るとこんな推移になっています↓
https://hisesshoku-derm.com/archives/2025/09/post_16.php
「これを見ると逆に減っているのは......
内科、小児科、外科、耳鼻咽喉科ですね?」
そうですね、白木さん。
増えているのは整形外科、皮膚科、
産婦人科、眼科です。
▼皮膚科が伸びているのは?
「皮膚科は伸びているんですね」
ええ。そのようですね。
皮膚科の調剤医療費を見てみましょう。
令和6年度は5,775億。
前年度から1,669億伸びています。
「ずいぶんと増えていますね。
いったい何が増えているんでしょうか」
令和6年度も注射薬で大幅な伸びが見られました。
◇「注射薬」薬剤料(単位:億円)
平成30年 4
令和元年 30
令和2年 54
令和3年 105
令和4年 152
令和5年 239
令和6年 671
「すごい伸びですね!
でも皮膚科で使う注射薬ってなんでしたっけ」
白木さん......。
思い出してくださいね。
タンパク質をもとに作られた生物学的製剤です。
アレルギー性の炎症の原因となるIL-4/IL-13シグナル伝達を
阻害する、免疫調整薬です。
皮膚科ではおもにアトピー性皮膚炎の
治療に使われています。
アトピー性皮膚炎治療薬は
さまざまなメーカーの開発が進んでおり、
副作用が起きにくい、投与頻度が少ないなどの
注射薬も開発されてきているようです。
▼アトピー性皮膚炎診療ガイドラインの改訂
相次ぐ新規薬剤の発売を受けて、2024年、
3年ぶりに「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン」が
改訂されました。
注射薬を含む新規薬剤5種が
掲載され、使用が強く推奨されています。
「それで薬剤料が増加しているんですね」
そうですね、白木さん。
こうした新薬の使用対象が、
「重症・最重症・難治性状態」(2018年版)から
「中等症以上の難治状態」(2021年版)に変更されています。
より幅広い患者さんに、
さまざまな新規薬剤を使用できるようになったことが
増加の一因でしょう。
これまでのステロイドの塗布だけでなく、
注射薬や経口薬など「全身療法」が
取られるようになってきたのですね。
今年度の医療費はどんな動向で推移しているのか。
また来年発表されたらお知らせしますね。
▼お知らせ:用語の変更です
『非接触生活』→『非侵襲生活』に。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
☆侵襲とは:
生体の内部環境の恒常性を
乱す可能性がある刺激全般をいう。
ここでは、皮膚の内部環境(バリア機能:細胞間脂質)
の恒常性を乱す要因です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
侵襲を受けやすい肌体質の人が、侵襲を受けない
生活(『非接触生活』→『非侵襲生活』)をしましょう、
ということです。
研究会としてこの方法をわかりやすく
知ってもらう活動を続けていきます。
☆ご相談・ご質問など、お気軽にどうぞ
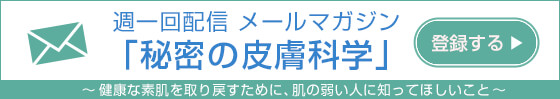
関連性の高い記事
【次のエントリー】
→ASVCの開発?『非侵襲生活』の秘密 | 第862号
【前のエントリー】
→ わかりやすさは?『改編7日間ステップメール』の秘密 ~その2~ | 第860号
![]()